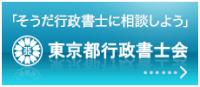相続についての「Q&A」は、
左側の「>相続について」の
リンクページからご覧ください。

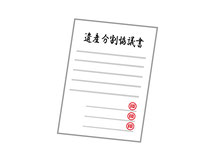
皆さんは、身近な方が死亡した際、
相続の手続きについて、
どこから手を付けたらよいのか
ご存知ですか?
家族が死亡したが、手続きをするのに
何から手をつけたらよいのかわからない、
遺言書がでてきたがどうすればよいか
わからないなど、
いざその時になって初めて浮かんでくる
疑問があるかもしれません。
また、葬儀や各所への連絡等で、
時間的・精神的に余裕が
無いこともあるかもしれません。
死亡者の戸籍を集めなければ
ならないが、自分で集める時間がない、
そもそもどこで取得し、どこまで
さかのぼって取得すれば
良いのかわからない、
遺産分割協議書を作成したいが、
どのように作ったらよいのか?など、
相続手続きについて
お悩み・お困りの方は、是非ご相談ください。
弊所では、相続人の調査、
相続財産の調査、財産目録の作成、
相続関係説明図の作成、
遺産分割協議書の作成、
預貯金や自動車の名義変更の手続き
などを行っております。
※不動産の相続登記につきましては、
ご希望により司法書士、
税務申告につきましては、
ご希望により税理士をご紹介いたします。
(行政書士は業務として行うことができないため)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
★「姻族関係終了届」について
配偶者が死亡した後には「離婚届」を提出することができません。
もし、配偶者(夫や妻)の死亡後に、配偶者の血族
(夫や妻の親や親戚)と縁を切りたい・関わりたくないと
希望する場合、生存配偶者は「姻族関係終了届」という届を
自治体(本籍地またはお住まいの自治体)に提出することで、
姻族関係を終了させることができます。
この届けに提出期限はなく、
配偶者の死亡届の提出後であれば、
届けの提出は可能です。
死亡した配偶者の血族の扶養義務はありません。
死亡した配偶者の遺産相続をした場合でも、
相続分の返却の必要はなく、
相続分について受け取ることは可能です。
ただし、注意点があります。
1.あくまでも届出をした配偶者との姻族関係は終了しますが、
死亡した配偶者との間に子供がいる場合、その子供と死亡した
配偶者との関係には影響しません。
2.姻族関係を終了させたとしても、戸籍へ反映されることは
ありませんので、結婚前の苗字に戻したい場合は、
姻族関係終了届とは別に、「復氏届」を提出することが必要となります。
★自治体のホームページからの申請書ダウンロードについて
最近はネットで探せば、
必要な申請書書類等をダウンロード
できるようになっている自治体が増えており、
便利になってきているとも言えるでしょう。
ただし、長期保存が必要な書類は、
紙質の問題から、あえてダウンロード不可とし、
自治体での配布としているところもありますので、
ご注意ください。
★固定資産税の縦覧制度について
23区内に不動産(土地・家屋)を所有
している納税者は、
たとえば2018(平成30)年の場合、
4月2日から7月2日までの期間(土日祝日を除く、
9時から17時までの間)に、
自分が所在する土地・家屋の価格と、
同一区内の土地・家屋の価格を、
各区の都税事務所で比較できます。
これを縦覧制度といいます。
縦覧には、納税者本人であることを
確認できるもの、代理人であれば
代理人の本人確認が必要となります。
※固定資産課税台帳の閲覧は、
他の土地・家屋との比較はできません。
★2018(平成30)年5月1日から、
固定資産に関する証明手数料と表示方法が変更に
対象となる証明:固定資産評価証明 ・関係(公課)証明 ・物件証明
手数料の改定
改定前 1件につき400円
➡ 改定後 1件目 400円 2件目以降 1件につき100円
※数え方は、土地1筆、家屋1棟、償却資産1種類ごとに1件。
※所有者、資産が所在する区及び証明の種類が同じ場合のみ。
※「土地又は家屋」、「償却資産」の別ごとに400円。
表示方法の変更
改定前 証明1枚につき1件 ➡ 改定後 証明1枚につき最大3件

遺言書や任意後見契約と
あわせて作成される方も
多くいらっしゃいます。
もし自分が、事故や病気で、
身体が回復困難な状態と
なった場合に、自分は
どのようにしたいと
考えたことはありますか?
昨今は、生命維持装置を
つけてまで長生きしたいとは
思わない、家族に迷惑を
かけたくない、などの考えから、
延命治療を行わず、
尊厳死を望む方が増加しているようです。
尊厳死宣言書とは、
「リヴィング・ウィル」とも呼ばれ、
本人が自らの考えで尊厳死を望むこと、
つまり、延命措置を控え又は
中止する旨の宣言を行う
書面のことを指します。
尊厳死宣言書の作成は、
公正証書により作成する場合と、
自著により作成する場合がありますが、
弊所では、公正証書により
作成する尊厳死宣言書のみ
お取り扱いを行っております。
なお、現状、尊厳死宣言書は
法律で定められた制度ではなく、
宣言書を作成したとしても、
最終的には医師の判断に
委ねられることになります。
そのため、必ずしも尊厳死が
実現されるとは限りませんが、
延命治療の中止について検討される
段階で、宣言した患者本人の意志を
推定し、確認する有効な手段とされる
可能性があります。
弊所では、尊厳死宣言
公正証書作成の
お手伝いをいたします。
ご自身の作成の意志、
作成にいたるまでの
お気持ちをご確認します。
その後、ご家族の同意を確認し、
同意書にいたします。
公正証書作成に必要な
書類などは弊所で取得し、
公証人との連絡調整、
打ち合わせも弊所が行う
ことが可能です。
遺言書、任意後見契約と
あわせての作成をご希望の方は
費用を割引いたします。
👉 万が一、作成した尊厳死宣言書が
拒否された場合でも、料金を返還
することはできませんので、
ご了承ください。
【受付時間】
平日 10:00~19:00
メール・FAXは24時間受付中
ホームページからのご相談予約も承っております。
ご相談予約の方法は下記のとおり3つございます。
①ホームページ内にある「ネット予約はこちら」の
ピンク色のタブをクリック→必要事項のご入力
②ホームページ内にある弊所メールアドレスから
メールフォームを立ち上げ→自由入力
③弊所メールアドレス
info@shibazaki.org
宛に直接自由入力
予めご連絡頂ければ、土日祝日や時間外も対応いたします。
出張相談も承ります。
ご連絡は下記へ
(行政書士には、法律で職務上知り得た
他人の秘密・情報を、他に漏らしては
ならない守秘義務が課されています。
安心してご相談ください。)
西武新宿線上井草駅北口より徒歩約5分
〒177-0042
東京都練馬区下石神井4-7-16
クアルト上井草109
しばざき行政書士事務所
行政書士 柴﨑(崎) 理佳
しばざき りか
電話: 03-6913-3979
(↑スマホからそのまま発信できます)
メール: info@shibazaki.org
(24時間受付)
(上記アドレスからメールフォームが立ち上がります)
FAX: 050-3588-7544
(24時間受付)
FAX用のお問い合わせ・相談フォームが
ダウンロードできます。
ダウンロードしたFAXのフォームを
ご利用・ご記入の上、上記のファクス番号まで
送信いただくと便利です。
もちろん、ダウンロードせずに
ご家庭に有る用紙をお使いになり、
ご相談・お問い合わせの内容がわかるように
お書きいただいてFAX送信して
いただいても構いません。

 東京都練馬区下石神井の(西武新宿線上井草駅北口より徒歩約5分)
しばざき行政書士事務所(東京都行政書士会練馬支部・下石神井商店街振興組合所属)
※女性行政書士が対応します※
平日10時~19時 (事前連絡で土日祝日時間外も対応)
☎ 03-6913-3979
📧 info@shibazaki.org
FAX 050-3588-7544 (メール・FAXは24時間受付)
※オンライン相談有り※
ホームページからの相談予約も受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください
遺言書・相続・成年後見などの終活全般、離婚などの暮らしに関する手続きを中心に、
各種許認可申請手続(内容証明・車庫証明含)など幅広い業務を行っております
〒177-0042 東京都練馬区下石神井4-7-16 クアルト上井草109
東京都練馬区下石神井の(西武新宿線上井草駅北口より徒歩約5分)
しばざき行政書士事務所(東京都行政書士会練馬支部・下石神井商店街振興組合所属)
※女性行政書士が対応します※
平日10時~19時 (事前連絡で土日祝日時間外も対応)
☎ 03-6913-3979
📧 info@shibazaki.org
FAX 050-3588-7544 (メール・FAXは24時間受付)
※オンライン相談有り※
ホームページからの相談予約も受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください
遺言書・相続・成年後見などの終活全般、離婚などの暮らしに関する手続きを中心に、
各種許認可申請手続(内容証明・車庫証明含)など幅広い業務を行っております
〒177-0042 東京都練馬区下石神井4-7-16 クアルト上井草109